はじめに
――「その1分」が、命を分ける
もし、あなたが職場でデスクワークをしていたとき、通路の向こうで同僚が急に倒れた場合
声をかけても反応がない。呼吸もおかしい気がする。足がすくむ——でも、そこで動けるかどうかが生死を分けます。
この記事は、そんな瞬間に「迷わず動ける自分」になるための完全ガイドです。
AED(自動体外式除細動器)の仕組み・特徴・使い方・注意点から、子どもや高齢者への対応、導入・点検のポイント、現場シナリオ、チェックリスト、よくある勘違いまで一挙にまとめさせていただきました。
是非ご参考ください!

むずかしく考えないでOK!
“音声の指示に合わせて手を動かす”のがAEDの基本ルールだよ!
手順はこの記事でしっかり練習しましょうね♪
- 第1章 AEDとは?何をする機械?
- 第2章 AEDの基本構造と特徴
- 第3章 “現場で迷わない”AED使用手順
- 第4章 安全と法的な配慮(やっていいこと・気をつけること)
- 第5章 よくあるQ&A集
- 第6章 “心理の壁”を越えるためのミニストーリー(シナリオ3本)
- 第7章 導入と運用
- 第8章 注意事項の深掘り(見落としやすいリスク)
- 第9章 チェックリスト(印刷・共有OK)
- 第10章 “数字で納得”の基本知識
- 第11章 職場での“運用ルール”テンプレ(そのまま流用OK)
- 第12章 ケーススタディ(導入効果の可視化)
- 第13章 自分ごと化のコツ(平時のたった3つ)
- 第14章 用語ミニ辞典
- 第15章 まとめ(今日からできる3アクション)
- おわりに
第1章 AEDとは?何をする機械?
ちなみにAEDとはこんなヤツです!

もしかしたら、皆さんも街中や会社とかで見たことある方いらっしゃるかもしれないですね!
使い方については講習受けたことあるけど忘れてしまった・・・という方が大半ではないでしょうか?
そこで、本記事でAEDの使用方法をおさらいしていただければと思います🐶♪
1-1 AEDの役割
AEDは、心臓がけいれん(心室細動など)で機能を失っているときに、電気ショックでリズムを整えるための機械です。ポイントは次の3つ。
・自動解析:心電図解析を機械が自動で行い、ショックが必要か判断する
・音声ガイド:音声と図解で、初心者でも順番どおりに操作できる
・安全設計:ショックが不要な場合は作動しない(意図せぬ通電を防ぐ)
1-2 「誰が使えるの?」
医療従事者でなくても使えます。むしろ早期の電気ショックと胸骨圧迫が救命率を押し上げるため、周囲にいる「あなた」が動くことが重要です。
1-3 「どこにあるの?」
駅、空港、学校、スポーツ施設、商業施設、オフィス、工場、自治体の公共施設などに設置が進んでいます。職場やよく行く施設の設置場所を、平時から把握しておきましょう。
第2章 AEDの基本構造と特徴
音声ガイドに従っていただければ、まず感電することはないでしょう…⚡
2-1 本体と電極パッド
・本体:電源ボタン、ショックボタン(半自動機)、スピーカー、インジケーター
・電極パッド:胸に貼る粘着パッド。成人用・小児用がある(機種により共用可)
・ケーブル/コネクタ:本体とパッドを接続
2-2 解析と通電の流れ
①電源ON → ②音声ガイド開始 → ③パッド貼付 → ④解析(触れない) → ⑤ショック指示なら「全員離れて」→ ショック → ⑥すぐ胸骨圧迫再開(2分目安)
※ショック不要と判定されたら胸骨圧迫を続けます。
2-3 わかりやすい強み
・手順がシンプル(音声に従うだけ)
・誤ってショックする危険を避けるための安全設計
・子どもにも配慮(小児モードや小児用パッド)
2-4 よくある誤解
・「素人が使っていいの?」→ 使っていい。使うべき機器。
・「壊したらどうしよう」→ 頑丈で、日常点検で故障は気づける。
・「感電が怖い」→ 通電時に触れなければOK。合図と確認が大切。
第3章 “現場で迷わない”AED使用手順
緊急時は「判断」より「手順」。
以下を声に出して実行すると、周囲も動きやすくなります。
3-1 現場の安全確認
・車や機械、電気、水濡れなど危険がないか確認
・危険があれば可能な範囲で除去、または安全な場所へ移す
3-2 反応・呼吸の確認(10秒以内が目安)
・肩を叩き「大丈夫ですか?」と声かけ
・普段どおりの呼吸がない(あるいは不自然なあえぎ)なら心停止を疑う
3-3 119番通報・AED手配・役割分担
・「あなたは119番を!スピーカーフォンで!」
・「あなたはAEDを持ってきて!」
・「あなたは人を集めて周囲を広く空けて!」
3-4 胸骨圧迫の開始(AEDが到着するまで途切らせない)
・胸の中央(胸骨の下半分)を、成人は約5〜6cm沈む強さ、1分あたり100〜120回のテンポで、しっかり早く押す
・体重を垂直にのせ、元の位置までしっかり戻す(完全リコイル)
・人工呼吸は可能なら30:2、できなければ圧迫のみでもよい(圧迫の中断を最小化)
3-5 AED到着後
①電源ON(ふたを開けるタイプもある)
②音声ガイドに従い、胸を露出(濡れは拭く・体毛は必要時にシェーバーで)
③パッド貼付(成人):
・右鎖骨の下(胸骨右側上部)
・左乳房外側の下(心尖部側)
④解析中:「離れてください!」と周囲に宣言。体に触れない。
⑤「ショックが必要です」→ 全員離れているか目視・声で確認し、ショックボタンを押す(自動機は自動通電)
⑥ショック直後:ただちに胸骨圧迫を再開(2分目安)。その後も音声指示に従い、解析・ショック・圧迫を繰り返す。
3-6 貼付時のコツ(迷いやすいポイント)
・胸が濡れている→タオルで素早く拭く
・濃い体毛→同梱のカミソリで貼付部をさっと剃る(時間をかけすぎない)
・ペースメーカー(鎖骨下に硬い膨らみ)→そこを避けて数cmずらす
・貼付薬(ニトロなどのパッチ)→手袋で剝がし、残渣を拭ってから貼る
・ブラジャーのワイヤー・アクセサリー→パッドの妨げになれば外す(時間をかけすぎない)
3-7 子ども・乳児への対応
・小児モード/小児用パッドがあれば使用(対象年齢・体重は機種表示に従う)
・乳幼児では前後貼り(胸の中央と背中の肩甲骨間)を採用する機種もある
・なければ成人用パッドでも実施(パッド同士が触れないよう前後貼りを検討)

“ショックのあとはすぐ圧迫”が鉄則だよ。
解析や搬送で止まりがちだから、“2分サイクルを合言葉”にしましょうね!
第4章 安全と法的な配慮(やっていいこと・気をつけること)
焦りは伝染してしまいますからね。
まずは落ち着いて音声ガイド通り対処しましょう!
4-1 安全の基本
・通電時は「全員手を離して!」をはっきり宣言し、接触をゼロに
・水たまりや金属床は避ける(移動できなければ可能な範囲で絶縁)
・酸素(医療用酸素)使用中は通電時に酸素流を患部から離す
4-2 記録と引き継ぎ
・救急隊到着後は、実施したこと(圧迫開始時刻、回数、おおよそのサイクル、ショック回数、反応の変化など)を口頭で引き継ぐ
→大体で大丈夫ですよ。
・AED本体の記録(データ)を救急隊に渡すよう求められることがある
4-3 法的・倫理的な視点(一般論)
・善意の応急手当は、社会的に求められている行為です。積極的に救助しましょう。
・個人の貴重品に配慮しつつ、生命の安全を最優先に行動する。
(注:具体的な法制度・免責の適用は地域・状況で異なり得ます。勤務先のルールや自治体の救急講習で最新の説明を確認しておきましょう。)
男性が女性に手当する場合はセンシティブな問題になります。
これに関しては私もいまだに正しい行動が分かりません。。
セクハラのリスクもありますよね。。どうしたら良いのでしょう。。
第5章 よくあるQ&A集
全部で20個の質問をいただきましたが、基本落ち着いてかつ常識の範囲内で
行動していただければ大丈夫です!
冷静さが一番大事です!!笑
Q1:胸骨圧迫が弱くならないコツは?
A:肘を伸ばして真上から体重を乗せ、手の位置がズレないよう衣服のしわやボタンを目印にする。2分ごとに交代要員を決めておく。
Q2:人工呼吸は必須?
A:できる人・できる環境なら実施。できないなら圧迫を止めないほうが優先度は高い。バリアやポケットマスクがあると安心。
Q3:パッドの向きが分からない
A:パッドの図を見て、その通りに。迷っても「右上・左下」の対角を意識。触れていけない解析中は“手を離す”。
Q4:金属ネックレスや貼付薬は?
A:パッドの妨げになれば外す。薬パッチは手袋で剝がして拭く。金属はパッドに触れない位置なら支障が少ない。
Q5:体が濡れている
A:素早く拭く。通電時の感電リスクと貼付不良を避けるため、濡れを残さない。
Q6:極端に寒い・暑い場所
A:パッド接着が弱くなることがある。皮膚を乾かし、密着を指先で圧着する。日常点検で保管環境を管理。
Q7:ヒゲ胸(体毛濃い)
A:同梱のカミソリでサッと剃る。電極が密着しないと解析・通電が効かない。
Q8:子どもに成人用しかない
A:ためらわず成人用で実施。ただしパッド同士が触れないよう前後貼りを検討。
Q9:ショック後に反応が戻った気がする
A:それでも“観察しながら胸骨圧迫”が基本。明らかな呼吸・意識の回復があれば体位を整え、再悪化に備えて観察。
Q10:職場で自分しかいない
A:スピーカーフォンで119番しながら圧迫→近くの人が来たらすぐ役割分担。AEDが遠いなら通報を優先し、圧迫を中断しすぎない。
Q11:感染が心配
A:手袋・バリアを常備。人工呼吸は無理せず、圧迫の継続を優先。
Q12:ペースメーカーがあるか分からない
A:鎖骨下の硬い膨らみで推測。あれば数cm外して貼る。分からなければ通常位置でよいが、金属の直上は避ける。
Q13:うまく貼れない・しわになる
A:皮膚を軽く伸ばしながら中心から外へ空気を抜くように圧着。
Q14:通電が怖い
A:通電時は「全員離れて!」を宣言→肩・足・衣服・ベッド柵などの接触を“目で”確認。
Q15:AEDが作動しない
A:電源・バッテリー・パッドの期限切れが原因になりやすい。日常点検で予防。
Q16:人工呼吸の空気が胃に入る
A:吹き込みは胸が上がる程度に。力強すぎ・速すぎを避ける。
Q17:ショック不要と判定された
A:胸骨圧迫を継続。リズムは変わり続けるので、解析のタイミングで再評価がある。
Q18:狭い場所・機械だらけ
A:最低限、胸骨圧迫できるスペースを確保。人払い役を明確化。
Q19:搬送中は?
A:揺れる環境での圧迫は質が落ちやすい。ローテーションや器具の活用は救急隊の指示に従う。
Q20:記録はどう残す?
A:開始時刻、ショック回数、反応の変化をメモ(スマホのメモでOK)。救急隊へ引き継ぎ。
第6章 “心理の壁”を越えるためのミニストーリー(シナリオ3本)
シナリオ1:製造ラインでの突然の倒れ込み
・安全確認→反応・呼吸確認→119・AED指示→圧迫開始→到着→貼付・解析・通電→2分ごとに交代
・ポイント:音と人の往来が多い。声を大きく。「赤いコーンで立入制限」「アナウンスで静かに」を即指示。
シナリオ2:スポーツ施設での運動中の倒れ込み
・汗と水濡れで貼付不良が起きやすい。拭き取りを迅速に。
・ポイント:観客や仲間が集まる。圧迫担当と人払い担当を分ける。スマホのスピーカーフォン通報を明確化。
シナリオ3:オフィスの会議室
・机や椅子でスペースが狭い。2〜3人で迅速に片側へ寄せ、床に寝かせる。
・ポイント:オフィスのAED設置場所を普段から共有し、エレベーターの動線を空ける。
実際にうちの会社ではシナリオ1で試したことがあります!
あるあるだと思うけど、役割に抜擢された人はとっても嫌そうなリアクションになりますよね!(笑)
日頃いじられキャラの人がやると更に盛り上がりますね♪

“大きな声で役割を伝える”だけで現場の空気が締まるよ。
『あなたはAED!あなたは119番!あなたは人を下げて!』って短くハッキリね!
でも楽しく学ぶのが一番♪
第7章 導入と運用
7-1 設置の基本
・人の集まる場所、移動しやすい動線、目につく高さ(サイン表示を大きく)
・防塵・防滴・温度環境の確認(製造現場は特に)
・鍵なし・ガラス扉など、取り出しやすい収納
7-2 点検・保守
・日常点検:インジケーター(OK表示)、電源入るかの自己診断表示、異音や破損の有無
・定期交換:電極パッドの使用期限、バッテリー交換時期
・付属品:はさみ、タオル、カミソリ、手袋、バリア、ティッシュ、ブランケット
・点検記録:日付・担当者・状態・交換記録を残す(紙/デジタル)
7-3 教育と訓練
・月1回、5分のミニ訓練(「電源オン→パッド貼る→“離れて!”→圧迫再開」)
・四半期に一度のロールプレイ(製造ライン/事務所/倉庫などシーン別)
・普通救命講習(地域の消防・赤十字など)を年1回以上
7-4 事故後のケア
・実施者の心理的ケア(デブリーフィング)
・関係者への情報共有(個人情報に配慮)
・再発防止策の見直しと環境改善
第8章 注意事項の深掘り(見落としやすいリスク)
8-1 環境要因
・水場、冷蔵・冷凍庫前、油分の多い床、粉じん環境では転倒や滑りに注意
・騒音が大きい現場は合図が聞こえにくい。通電前は“目視確認”もセットで
8-2 電気・静電気
・除電ブラシや金属フレームに接触したまま通電しない。身体・衣服が触れていないか、手で肩・足・服・ベッド柵をなぞるように目で追う
8-3 寒冷・高温
・寒冷地ではパッド接着が弱くなる。押さえ圧着を丁寧に。
・高温環境での保管は電極ゲルの劣化を招く。設置環境を見直す。
8-4 ペースメーカー・ICD
・膨らみの上は避ける。数cm外へずらせばOK。解析・通電の妨げを減らす。
8-5 貼付薬・皮膚病変
・貼付薬は剝がす→拭き取る→貼る。皮膚病変は出血を避け、健常皮膚に密着させる。
第9章 チェックリスト(印刷・共有OK)
簡単にはなりますがチェックリスト作成させていただきました♪
是非ご参照ください!
【すぐ使える30秒版】
□ 周囲の安全はOK?
□ 反応・呼吸は?(10秒以内)
□ 119番・AED手配・人払いを“指名”した?
□ 胸骨圧迫を開始した?(100〜120/分・5〜6cm)
□ AED到着→電源→パッド貼付
□ 解析中・通電時は“全員離れて”を宣言
□ ショック後はすぐ圧迫再開(2分サイクル)
□ 救急隊へ実施内容を引き継ぎ
【点検・備品】
□ インジケーターOK/自己診断OK
□ 電極パッドの期限内
□ バッテリー残量十分
□ はさみ・タオル・カミソリ・手袋・バリア・ブランケットあり
□ 点検記録の更新第10章 “数字で納得”の基本知識
・心停止からの時間経過が長いほど救命率は低下。早期の胸骨圧迫とAEDが鍵。
・胸骨圧迫の質(深さ、テンポ、完全リコイル、中断最小化)が生存退院率に直結。
・「最初の人が押し、次の人が支える」チーム化で質を落とさない。
第11章 職場での“運用ルール”テンプレ(そのまま流用OK)
もう少し短縮して、職場内に掲示するだけでも潜在意識に刷り込まれて効果アリです!
1)目的:心停止発生時に速やかな胸骨圧迫とAED使用で救命率を高める
2)体制:各部署に応急手当リーダー配置、月次ミニ訓練を実施
3)設置:人の往来が多く目につく場所、サイン掲示、動線確保
4)点検:週1インジケーター確認、月1消耗品確認、年1パッド・バッテリー計画交換
5)訓練:月1ロールプレイ5分、四半期ごとにシナリオ訓練、年1外部講習
6)記録:点検表・訓練記録・インシデント記録を保存
7)広報:社内ポータルに設置場所と手順動画、119・AED連絡フロー掲示
第12章 ケーススタディ(導入効果の可視化)
KYTのネタがなくなった時は、これらのケースについて話し合っても良い機会になりますよ。
ケースA:製造現場
・課題:騒音・機械の密集・通路狭い
・対策:サイレン付きAEDボックス、赤コーン常備、人払い係を事前指名
・効果:通報〜圧迫開始までの時間短縮、通電前の接触ゼロを徹底
ケースB:商業施設
・課題:休日の人だかり、パニック
・対策:フロアマップにAEDを重ねて掲示、警備と連携マニュアル化
・効果:AED到着時間の安定化、野次馬の削減
ケースC:オフィス
・課題:設置場所が知られていない
・対策:朝礼で「AEDまでのルート走」、社内チャットで月1リマインド
・効果:設置場所の想起率向上、初動の迷いが激減
第13章 自分ごと化のコツ(平時のたった3つ)
・設置場所を脳内に刷り込ませる
・現在地から「ここから何秒で現場へ?」をイメトレ
・「離れて!」の声出し練習を1回だけやる
日頃から大きい声出せると緊急時は良いですね。
ただ、職場でいきなり大声を出すと色々と大変なので気を付けましょう!
やるなら家でお願いします!

完璧を目指さなくてOK。“最初の1分で行動する人”がヒーローだよ!
第14章 用語ミニ辞典
一応紹介させていただきます!
余力がある方は覚えておいても損はありません。
・除細動:乱れた心室の動きを電気ショックでリセットすること
・心室細動(VF):心室がけいれんし、血液を送り出せない状態
・無脈性心室頻拍(pVT):早い心拍で脈が触れない危険な状態
・BLS:一次救命処置(胸骨圧迫・AED・気道管理など)
・完全リコイル:押し込んだ胸を元の位置まで戻すこと
第15章 まとめ(今日からできる3アクション)
1)職場・よく行く施設のAED設置場所を3つ覚える
2)声出しフレーズを3つ覚える(「119番お願いします」「AEDお願いします」「離れて!」)
3)月1回5分のロールプレイをチームでやる
何が大事かというと、日頃から危機意識を持ち
あらゆる場面を想定しておくことですね!
おわりに
読了、ありがとうございました!
ここまでの知識があれば、いざという時に「自分が最初に動ける人」になれるはずです!
心停止は突然に起きます。
完璧じゃなくてもいいんです。
勇気を出して、最初の一歩を踏み出しましょう!
なお、地域の消防や赤十字などが開催する救命講習を受ければ、実技で自信がつきます。
職場の仲間と一緒に受講するのもおすすめですよ♪
それでは!今日もご安全に🐶


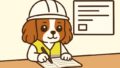
コメント