急な体調不良やケガで「救急車を呼ぶべき?」と迷った経験はありませんか?
実はそんなときに役立つのが、全国的に広がっている「#7119(救急安心センター)」です。
この番号に電話すると、看護師や医師などの専門家が24時間体制で相談に応じてくれます。

救急車呼ぶかどうか迷ったら#7119
これは絶対覚えてね⭐️
どうして#7119が必要なの?
日本では年間およそ600万件以上の救急出動があります。
しかし、その中には「緊急性が低い」事例も少なくありません。
例えば、夜中にお子さんの熱が上がったり、転んで擦りむいたりしたときなど。。
「本当に救急車を呼ぶべき?」と迷った経験はありませんか?
実際に救急車を呼んだら「自家用車でも十分搬送できた」というケースもあれば、逆に迷って様子を見てしまい症状が悪化するケースもあります。
#7119は、こうした判断の難しさを解消するための電話相談窓口です。
専門家が症状を丁寧に聞き取り、必要なら救急搬送を勧め、緊急性が低ければ自宅での対応や翌日の受診を案内していただけます。
使い方はとても簡単!
スマホでも固定電話でも「#7119」を押すだけです!
お住まいの地域によっては別の番号に転送される場合もありますが、基本的には共通番号として全国で利用が進んでいます。
通話料は有料ですが、相談自体は無料です(※通話料は携帯や固定電話のプランによります)。
相談の流れ
- 電話をかける
- 看護師や医師が症状をヒアリング
- 必要性に応じて対応を案内
- 救急搬送が必要な場合:すぐに119へ
- 自宅で様子を見る場合:対応のアドバイス
- 翌日の受診でよい場合:適切な診療科を案内

これならメルちゃんでもできそう🎵笑
7119のメリット
- 救急車の適正利用が進む
- 利用者が安心して判断できる
- 医療機関の混雑を緩和できる
- 夜間や休日でも専門家に相談できる
特に小さなお子さんや高齢者のいるご家庭では、突然の体調不良で迷うことが多いはずです。。
「夜中に熱が出たけど、すぐ救急車が必要なのかな…」というときも、#7119ならプロが冷静に判断してくれます。
ちなみに私は#7119にかけた経験がないので、かけたことがあるという方は是非実際の流れを教えていただけると助かります🎵
企業にもメリットがある
実は#7119は、一般家庭だけでなく企業でも活用できます。
例えば工場でケガをした社員が出た場合、「救急車をすぐ呼ぶべきか、それとも応急処置で足りるのか」を判断できます。
従業員の安全管理やBCP(事業継続計画)の一環としても役立ちます。
また、社員に周知しておけば、休日や出張先での急病時にも安心です。
企業としては「救急車の乱用を避けながら従業員を守る」ためのツールとして位置付けられます。
よくある質問
Q. どんな症状でも相談できる?
A. 急な発熱、けが、胸の痛み、頭痛、腹痛など、救急搬送が必要か迷うときはどんな症状でも相談可能です。
Q. 直接119にかけた方がいい場合は?
A. 意識がない、呼吸が苦しい、出血が止まらないなど命に関わる症状は、迷わず119へ!
Q. 全国どこでも使えるの?
A. 一部地域を除き、ほぼ全国で利用可能です。地域によっては前述させていただいた通り別番号に繋がる場合もあります。
同僚の体験談
私の同僚は、深夜に子どもが急に嘔吐して熱が上がったとき、#7119に相談したそうです。
電話口で症状を丁寧に確認していただき、「今すぐ救急車は不要。水分補給と熱の経過観察をして、翌日受診してください」とアドバイスを受けたそうです。
パニックになりかけていましたが、声をかけてもらえただけでも安心感があったと高評価でした!
今もそのお子さんは元気に過ごしています🎵
同僚の体験談から、改めて正しい知識と迅速な対応の大切さを感じることができました。
まとめ:知っておくと命を守れる番号
救急車を呼ぶか迷ったら**#7119**へ
専門家が24時間対応
緊急性の有無を判断してくれる
一般家庭だけでなく企業でも有効

もしものときのために覚えておくと安心ね!
この記事をご覧いただいた皆さまへ
スマホの連絡先に「#7119 救急相談」と登録しておくと安心です。
いざというとき慌てずに対応できるよう、家族や同僚にもシェアしておきましょう!

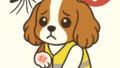

コメント